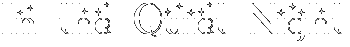
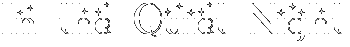
|
がたたっとケータイの振動のせいで机から音が鳴る。すでにウトウトとベッドの中で睡魔に誘われとったちゅーに邪魔するヤツは誰や。疎ましくも感じながら怠惰にも腕を伸ばしただけでケータイを探る。ディスプレイの表示には、。先程の眠気や面倒くささや全てが吹っ飛んですぐにケータイを開く。立ち上がって窓辺を覗けばすでに街には電灯の明かりしか灯っていなかった。 「なんやこないな時間に・・・」 「・・・・・・」 「おーい、もしもーし」 「・・・・・・」 「なんや悪戯か?切るで」 「・・・ひかるぅ」 「・・・どないしたん」 電波を通じて聞こえるの声はいつも聞く声の大きさより小さく感じた。弱々しく自分の名前を呼んで、泣いとるんとちゃうか、と思ったけどすすり泣きは聞こえない。ゆっくりと息を吐いて窓辺に寄って、窓を開ける。外気がすうっと肌に触れる。まだこの季節は肌寒い。 「黙っとったらわからんやろ」 「もういやや・・・」 「なにが・・・」 一瞬自分のことかと思ってドキリと心臓が脈打つ。けれどの次の言葉にほっと安堵した。 「こないな場所でやってける気ぃせん・・・」 「なに弱音吐いとるんや、初っ端から」 「はよ大阪帰りたい、光に会いたい」 あまり甘えた事や弱音を言わないがそんな事を言ったせいで、深夜に俺の胸はざわざわとざわめきだつ。ライン一本で繋がっているその声に、俺は愛しくも、そして切なくも想っていた。けれど不器用な俺にはそれを口にすることができへん。淡々と、の心を解すだけ。 「そっちはどうなんや、なんかあったんか?」 「なんかあったから電話しとるに決まっとるやろ、アホ・・・」 「なら原因をはよ話せや」 「こっちの人、冷たいんや・・・なんでジロジロ見るん?なんでそない愛想悪いん?大阪はそないとこやないやろ」 「せやなあ・・・ま、標準語んとこひとりぽっと大阪弁バリバリ喋るヤツおったら見られるんちゃうん?」 「でも愛想悪くすることないやろ」 「お前そっちの学校行き初めて何日目や」 「・・・一週間」 「アホ、まだ何も知らへんのと一緒や」 すると少しぐすぐすと鼻を鳴らし始める。あかん、ちぃとキツすぎたか?けれど俺のそんなセリフにむっとしたのか、は鋭く反論する。 「光はこっちに来てへんのやから分かるわけないやろ!めっちゃ心細うてかなわんのになんでわかってくれへんの!」 「・・・・・」 「それとも光はわたしがそっち戻って標準語べらべら喋って平気なん?全然さみしゅうない、こっちで元気しとるって言えばええの?」 「そないなこと言ってへんやろ」 「こっち来て光一度もメールしてくれへんやないの!」 「・・・・・・」 が本題として言いたいことは分かった。俺が、全く連絡よこさんからや。それはな、本当はな。そう言いたい。けど素直になれへんのと、どっか遠くで自分を見つめててくさいセリフを言う自分にむずがゆく感じるから。が大阪にいたころはほとんどメールのやり取りで、そんで昼間は学校で会って。一週間離れて、遠距離恋愛、ってこんなもんかって思い始めてた。さみしい、と思い始めてた。 「なんで黙るん」 でも今に俺の表情は見えない。俺が眉根をひそめてるのも、自分に会いたい、って顔しとるのも。分からへん。は声でもどんな顔をしとるのかわかるのに。俺はいつでも冷静でかったるそうやってお前が笑いながら言っていたのを思い出す。 「・・・さみしい、のは俺も一緒や」 「え・・・」 「お前のそのやかましい声学校で聞けへんの、なんや意外とさみしーなー思うとった」 「・・・・・・」 「正直、はよ、戻ってきてほしい」 「ひか・・・」 「でもな、お前まだ戻れんのやろ。そないな事言うたら余計会いとうなる、自分困らすだけやろ」 「光が自分の気持ち言うの・・・珍しい」 「・・・っ、自分のため思うて言っとんのや!」 「・・・フフッ」 「なに笑うとんのや!」 「光、かわいい」 「なっ・・・かわいい・・・?!」 クスクス笑うに俺は戸惑ってこんなこと言うの初めてやからどう対応すればいいのか分からへん。ちゅーかマジ恥ずかしい。なんやこれ、自分かっこわる! 「笑うのやめへんか!」 「しゃーないやろ、光が面白いこと言いよるから・・・」 「面白いことお?!こっちは大真面目やで!」 「光、そない声張りあげたら近所迷惑やで」 「・・・・・・っ」 未だにゲラゲラ笑うに俺は先程までの心細うてさみしいなんてうさぎのようにかわいいこと言っとったヤツとは思えへんかった。なんやこいつ。 「・・・光」 「あ?」 「ありがと」 「あり・・・?あ、あぁ・・・」 「こないな事聞けるんなら遠距離も、悪ぅないな」 「ずっと遠距離がええんか」 「それはいやや!」 意気込んで即答するに俺はプッと吹き出したが、同時にとてもかわいいと思った。いつもは甘え知らずで素直じゃないも、たまにはええかもしれへん。なんや、俺も気持ち悪うこと言うけど。 「明日も学校あるやろ」 「当たり前やんか、明日は水曜やで」 「ほな、はよ寝ろ」 「・・・・・・せやな」 「・・・・・また電話する」 「光がしてくれるん?」 「・・・まぁ、たまには、な」 「ほな待っとるから!おやすみー」 「おやすみ」 電話を自分から切るのが名残惜しくてそのままにしておいたらしばらくの沈黙の後ツーツーと向こう側から聞こえてくる。ラインが切れた。こんなもろい線で今繋がってる俺とは何度この切ないやり取りを繰り返すのだろうか。会いたい、なんて言うのはたやすくない。でもそれは近くにいるからで、素直にならずとも日々過ごす時間が解決してくれていた。着信履歴を見て、の名前を確認する。気がつけばまた、通話ボタンをおしていた。 「・・・どないしたん?」 「分からへん」 「・・・光?」 「・・・・・・寝る。おやすみ」 「・・・もう、なんなん?おやすみ」 「おやすみ」 「おやすみ」 なぜかもう一度声が聞きたくて、「おやすみ」と言いかけた。でも今度は自分から切った。ツーツーと音は聞こえない。机に置いてあるデジタル時計を見ればすでに時刻は三時になろうとしている。先程開けた窓から入った冷たい空気に今更ブルリと震えて寒さを実感した。の声は、あんなにも温かい。 「おやすみ」 静かな夜に俺の声だけが響いた。もう返事をする声もない。この殺風景の部屋に、俺との写真を飾ろうか。先輩たちに「どないしたん」と言われるのは覚悟の上で。 |