|
「弦一郎…」 「」 頬に触れる、大きな、手の平 弦一郎の大きな手の平が大好き 私の小さなちっぽけな手とは全然違う、ごつごつとした男らしい、大きな大きな手 その手が、頬に触れるだけで、私はぴくりと身体を震わせてしまう 私の手とは全然違う、少しかさついた、熱いあつい、大きな手 私を一瞬で包み込んでくれる その手が、指先が 私の肌に触れると思うと 男らしいその手が 私の身体にどうやって触れるのかを考えると たまらなくなって、私は今日もぴくりと身体を震わせてしまうんだ 「…む、す…すまん」 頬に触れられた手は、一瞬で離れてしまう すまん、の意味が分から無くて、は目の前の真田を見上げた もっともっと、触れてくれてもいいのに いや、もっともっと、触れてほしいのに 真田は、どうしてか、にあまり積極的に触れようとしない 熱い手の平の熱が恋しくて、は目の前の真田の胸へと身体を寄せた そして、見上げたまま、素直に願いを口にする 「…もっと…触って」 呟きと共にきゅっと身体を押し付けると、真田の口から声にならない声が上がった くっついた身体から、とくとくと真田の鼓動が聞こえる けれど、それはの鼓動も同じ 真田の身体に押し付けた胸から、いつもより早い、心臓の音が聞こえる 「し…しかしだな」 「触って欲しいの…。弦一郎は…嫌?私に、触りたく無い?」 は、誘う様にもう一度、きゅっと胸を押し付ける 「私は…弦一郎に触りたいよ。触っても、いい?」 恐る恐る、真田が先程そうした様に、彼の頬に手を伸ばす じりじりとした空気に、心臓がとくんとくんと大きな音を立てる 指先が、震えそう 「…構わん」 落とされた視線 固く結ばれた口元 その真田の様子に、胸がきゅぅっと締め付けられ、は静かに彼の首へと両手を回した 「弦一郎」 名前を呼ぶと、ぎゅっとさらう様に引き寄せられ、 なのに唇は優しく、そっと重ねられる 骨張った感触、広い胸板に、は長い睫を瞬かせた後、ゆっくりと瞳を閉じた 所在なさそうに下りていた手が、そろそろとの背中へと回されると、 まるで夢心地みたいに足元がふわふわしてくる もう、何度目のキスか分からないのに、 真田とするキスは、理性も、思考もとろとろのぐるぐるになるみたいで くるりと視界が反転し、天井が目の前に広がる その視界をネクタイを緩める真田の姿に遮られて、自分が押し倒されたと気付いた 「あっ…」 ごつごつとした男らしい指が脇腹を撫でて、胸に辿りつく ゆるゆるとそのまま何度か揉むと、 それでは物足りないというように、下着のホックが外されてしまい、 は小さく喘ぎを漏らした 続けられる口づけの合間に漏れる熱は、真田のか、自分のか 溶けて混ざりあい、どちらのかも分からない 弾けて自由になった胸を、真田の大きな掌が包む 持ち上げるように掴まれ、回すように揉まれる シャツの上から、下着越しの愛撫 時々掠める胸先への刺激 それが焦れったくて、物足りなくて 自分のシャツの上でいやらしく動く、真田の大きな手を想像して、は身をよじった 「んっ…や…」 その声に、真田の手はぴたりと止まる がうっすらと目を開けた時には、既に覆いかぶさっていた彼の姿は無かった 「…弦一郎…?」 何かを言いかけて、顔を少し赤くした真田は、そのまま、何も言わずにの腕を押し返した 「そろそろ帰る時刻だろう。送っていく。支度をしろ」 じんじんと、揉み回された胸が熱を持つ じりじりと、掠められた先端が疼く なのに彼の手は、もうに触れる事は無かった 「…で、また出来なかったと」 「うん」 次の日の放課後 真田の部活が終わるのを待つ間の、ゆっくりとした時間 外はすっかり陽が傾き、窓からは夕日が差し込んでいた 向かい合わせに座る紫樹は、あからさまにしゅんと俯くを見て、苦笑する 「全く、何やってんだかね−真田も」 「私が…いや、なんて言っちゃったからかな」 あの時、思わず、いや、と声が出てしまったかもしれない その瞬間、真田の手が止まったのを思い返して、ははぁ…と小さく息を付いた もう、ずっとこうだ 付き合って短くは無い、むしろ、長い方なのに、二人は未だ至って無い訳で 昨日はやっとちょっと進んだ気がしたのに、 自分がいや、なんて事言ってしまったから それを部活終わり待ち仲間の紫樹にぽつりぽつりと話すと、 紫樹は俯くの髪をくしゃくしゃと撫でながら笑った 「ちがうちがう。いやん、なんて言われると男は余計に喜ぶもんでしょ、フツー」 「…仁王君は、いや、って言うと喜ぶんだ?」 「…アイツは、変態だからそん位じゃ喜ばない」 くくっと、笑う紫樹の仕草は、その、どっかの誰かさんとそっくり 付き合っていると、仕草や話し方が似てくると言うのは本当みたいだ 心が通い、お互いが何を考えているのか、何となくだが感じ取り、 少なくとも、こうしたら喜ぶとか、こうしたら悲しむとか そういう事が少しづつ分かる様になる 紫樹と仁王は、まんまそんな感じがして、とても羨ましい なら、自分と弦一郎はどうだろう 考えなくても、答えは出ている気がした 何故、どうして 触れたいのに、触れてほしいのに それを言葉にする事もままならないのだから どうしてだろう 想いは、同じだと信じたいのに 真田がしてくれる様に、自分も真田を優しく抱きしめたいのに 昨日だって 嫌なんかじゃ無かった もっと触れてほしかった 嫌だったのは、自分のものじゃ無くなっちゃうんじゃないかと思った位 どきどきと音を立てる心臓と、自分のとは思えない位の甘えた声で 弦一郎に触れられるのが嫌だった訳じゃ無いのに 声が…勝手に出てしまって 「紫樹ちゃんは…仁王君と初めてした時はどうだったの…?」 「え、私?えー?どうだったかな…」 紫樹は一瞬考える様な仕草を見せた後、直ぐに思い付いた様に顔をあげ、ニッコリと微笑んだ 「仁王を…犯しちゃったかな−」 「え…えぇ?」 「うん、そうだそうだ…後ろからタックルして、押し倒して、服剥いじゃったの」 「ほ…ほんとに…?」 が困惑するように問うと、紫樹は愉しそうにほんとほんと、と繰り返した 「だって普段からフェロモン垂れ流してっからさぁ…仁王見てるだけで、ムラムラしない?」 「そ…そうかなぁ」 仁王を、見てるだけで、ムラムラ? はそれが分から無くて首を傾げた ムラムラするのなら、真田のがムラムラする いや、実際ムラムラ、と言うのがどんな気分の事なのか イマイチよく分からないけれど あの、しゃんとした背筋に凛とした背中 鍛え上げられた腕に、大きな、分厚いくて固い手の平 真っ黒な髪に意志の強そうな瞳 すっきりとした鼻立ちに、薄く、引き締まった口元 涼しげな横顔を見ているだけで、何とも言えない気持ちになる ざわざわと背筋が音を立てて、心臓が不規則な音を立てて、 じんわりと身体中に甘いなにかが広がって、目が離せなくなる 触れたいなぁ、と思うのがそれなら、仁王よりも断然、真田にムラムラする 今、こうして話しているだけでも、真田を想像して、甘い疼きが身体を駆け巡る様な… 変な気分になってしまう 触りたい、触れたい、抱きしめたい もっともっと、深く深く、欲しくなる 大事に大事にされてるのは分かる 触られると嬉しくて、幸せで 自分も同じ様に、真田に触れたいと思うのに 「弦一郎は…私と…同じ気持ちじゃ無いのかな」 不安ともどかしさで、つい弱気な発言をしてしまう 心なしか、目尻にじんわりと熱いものが込み上げてきそうで そんなを見て、今まで笑っていた紫樹も、言葉を一瞬詰まらせた 「待たせたな、」 「帰るぜよ、紫樹」 声がした方を振り返ると、それぞれの待ち人が教室の外から顔を覗かせていた 「おそーい」 がたりと紫樹が慌てた様に席を立ち、俯いたを隠すように彼等に駆け寄る 「お疲れ様」 「うむ」 その隙にぱぱっと手で目尻に涙が浮かんで無いのを確認すると、 も真田の元へと駆け寄った 「じゃぁね、紫樹ちゃん…ひゃっ…」 それは、一瞬 くるりと振り返ろうとしたの胸に、にゅっと手が押し当てられて思わず変な声が出た むにゅむにゅとの胸を揉むのは紫樹の手 後ろから差し込まれた紫樹の両手が、容赦無くの胸を大きく揉みあげる 「な…何をやっとるか貴様!」 「えぇ〜?真田が構ってあげないからぁ、の身体が夜泣きしない様に〜ってね」 「な…っ…」 目の前で形が変わるほど揉まれるの胸を見て、真田の顔は一瞬で赤くなってしまう 開いた口が塞がらないとはこのことだろう 同じく視線はの胸から離せないらしく プルプルと震え出す真田の顔を見て、はたまらず身をよじった 「あ、あんっ…紫樹ちゃ…」 「なぁに、…ここが弱いの?」 「や…っぁ…っあんっ」 「こ…このたわけがっ…!!さっさとその手を離さんか!!」 真っ赤になった真田が、唾を撒き散らす程の大声で叫ぶと、 はいはいと呆れた様に返事をして、やっと紫樹がの胸から手を離した 「じゃーね、」 まだ何か言い足りない真田の脇を器用にすり抜けて、ひょいひょいと廊下へと逃げ出す紫樹 笑いを堪えきれないと言った仁王がその後を追おうとすると、 紫樹は再びくるりと振り返り、真面目な顔で真田を睨みつけた 「真田」 「む、なんだ。謝ってすむ問題では無いが、謝罪ならに…」 「女が抱いてって言ってんでしょ。男なら黙って受けてたちなよ」 紫樹の言葉に、真田の眉間に皺が寄る 紫樹の突然の言葉が、何を意味しているのか、理解した様に見えた ほんの少しだけ頬が染まった様に見えたのは、夕日のせいかもしれない 「お前が口を出す問題でも無かろう。それに…まだ早い。にはまだ…」 「それを決めるのはでしょ。真田はそれを受け止めればいーの」 「む…」 それだけ言うと、まるで言い逃げするみたいに、紫樹はパタパタと走って行ってしまった 唖然とその背中を見つめる中で一人だけ、堪えきれずに吹き出すものが一人 「くっくっく…」 「に、仁王!お前は…っ紫樹にどういう教育をしている!」 「…教育?そーじゃのぉ」 紫樹を追う足を止め、仁王はくるりと振り返る そして三歩真田に歩みよると、猫背のまま、 緩んだ口許を左手で抑えつつ、仁王は言った 「とりあえずは、愛してるって、ひたすら教えてやっとるよ」 「…」 「お前さんもそうじゃろ?」 そう言い残して仁王は再び紫樹の後を追う 仁王が去った後も、二人は少しの間、茫然と廊下に立っていた そして、視線を合わせる その後、二人して照れ笑い 「まったく…とんでもない奴らだ」 「ホントに」 「…」 「…」 もう陽も大分傾いた 廊下には二人の長い影だけがある 冬から春に移り変わる、澄んだ空気の中 この廊下に、たった二人 見つめ合っていた二人は、一瞬吹き抜けた冷たい風に、我に返った 「…帰るか」 「…うん。……あの…弦一郎、私」 「良い」 恐る恐ると言ったの言葉をぴしゃりと遮ると、真田はを正面に見据えた 「こういうのは、男から言うものだ」 「…うん」 頷くと、真田がやけに真剣な顔で見下ろし、肩を抱いて顔を覗き込んで来る 押し殺した声 激しい情動を讃えた切れ長の瞳が、を間近から射抜く 僅かに眉間に皺を寄せつつも、 見たことも無い程の真剣な表情を浮かべる真田には、もう迷いは無い様に見えた 「」 はっきりと真田が自分の名前を呼ぶ ただそれだけで、全身に甘い感覚が広がって、 その場にどさりと尻餅をついてしまいそう なのに彼は、更に自分をとろけさす言葉を続けたのだ 「お前をもらう」 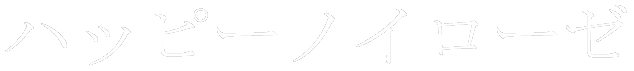 「本当にいいのだな」 ベッドの上で、正座した真田は、もう一度に問い掛ける 「うん」 「…最初に言っておくが、優しくするといった保証は無い」 苦い顔でそう言う真田に、は思わず眉を寄せた 「む、無論、出来るだけ優しく触れようとは思っている…しかしだな」 「弦一郎は…優しいよ、いつも」 が静かに、真田の手を取る 今日も真田の手は、ごつごつしてて、大きくて、暖かく、優しかった 「そんなに、宝物に触れる様にする事無いのにって、思う位、いつも、優しい」 取った真田の手を、ゆっくりと自分の頬に当てると、は愛おしそうに、ほお擦りをした 真田は、の行動と台詞に、硬直した様に動けないでいる 「弦一郎は、知らないんだよ…その大きな手が、ぎゅっと私を抱きしめてくれる度、 私、すごく幸せなんだよ」 「…しかし…俺が触れる度に、お前はびくびくと震えるだろう」 「え…?」 「本当は…怖がっているのでは無いのか」 その言葉にが微笑むと、真田はむ、とまたも難しそうな顔を浮かべた 「教えてあげたい。私が、どれだけ弦一郎を好きか」 「…そうか」 「私の手がもっと…弦一郎みたいに大きかったら、同じ様にぎゅっと出来るのに」 「何を言っている。お前はそのままで良い」 「そのまま…」 「うむ。難を言えば、もう少し肉を付ける事だ。俺の力で壊れてしまうのでは無いかと…思う事もある」 そうか、それで 「…では、教えてもらおう」 大きな手の平がの頬を包む あぁ、こうして弦一郎がしてくれるのと同じ様に、 私もこうして全部全部、大切に包んであげたい はゆっくりと重なる唇の感触にさらわれながら、そう思った 「あ、あのね」 キスを遮るに、真田は律儀に唇を離す 「なんだ」 「私…パイズリはした事無いから出来るか分からないんだけど…パフパフなら出来ると思うの」 「パイ…?ほう、聞き慣れん言葉だ。なんだ、それは」 「あ、やっぱり弦一郎も知らないよね?仁王君と紫樹ちゃんに聞いたんだけどねパフパフは、こう…」 言うなりは、自分の胸をきゅっと寄せて上げて、ぽよんとした谷間を作る まさかの光景に、弦一郎は大きく目を見開いたまま、口をぱくぱくとさせて硬直した 「こうしてね、ここに弦一郎のお顔を埋めるの。でね、パイズリって言うのは同じくこの間におちん…」 「な、何を言っておるこ、こ、このたわけがああああっっ…!!」 「え…違った…?」 「か、仮にも嫁入り前の女がその様な言葉を口にするとは、たったっ…たるんどる…!! そこになおれっ!キェェェェ…!」 キィィンと耳鳴りがする程の雷が落ちて、残ったのは涙目のと真っ赤に憤慨する真田の姿 その後くどくどと続くお説教に、は何が駄目だったのか分からず、 けれども真っ赤になった真田が可愛くて それに、真田の鍛えられた大きな身体で一カ所、 修業の足りて無い場所を見つけて、一人微笑んでしまうのだった 一花ちゃんへの応援夢小説 |