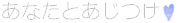「どうしたんだよ、。ボーっとして」
「なんでもない」
マグカップ片手にコーヒーの香ばしい匂いを立たせてシリウスは笑う。わたし達は騎士団で、死と隣合わせな場所に身を置いている。覚悟はある。けれどなんの危険も知らずに過ごせた学生時代のわたしは、もう帰ってこない。へいわ、なのかなあ。わたしが求めているのって。求めるのは白い鳩?それもなんかちょっと違う。
「そんな難しい顔してなんでもないなんて気になるだろ」
「だって言ったらまたバカだなあ、って言うもん」
ソファーの肘掛けに頭をもたげる不機嫌なわたしの隣にシリウスは腰掛ける。城の外へ出てしまえば、あの時の平和がどれだけ閉鎖的なものだったのかと思い知る。わたしがため息つくとシリウスはわたしの頭をぐいっと強引に膝の上に乗せた。
「お前はいつだってくだらない事しか考えてねーじゃん」
「くだらないことってなによー」
「は余計な心配しすぎ、ってこと。目の前にないものばかりにとらわれてたら、空を手につかんでるだけだろ」
確かにわたしの心配ごとって無駄なことばかりな気がする。特にシリウスがスネイプをけしかけてリーマスの変身した姿を見せちゃった時わたしは心配しすぎて貧血起こして倒れちゃったんだっけ。
「でもそれはシリウスがいけないんじゃん。昔からわたしに心配ばっかかけさせてさ」
「だーかーらー俺がそんなヘマすることなんてないだろ?」
「でもシリウスに何かあったら・・・って思っちゃうんだもん」
わたしは本当に心配性だ。それも半分はシリウスのせいだと思う。シリウスの膝からごろりと転んでカーペットの床へとどすんと落ちた。フンだ、心配かけるシリウスなんて嫌いだ。だって、平和じゃない。もし死喰い人と戦って死んでしまったら?もしディメンターが何かの間違いで襲ってきて魂が抜かれてしまったら?もし拷問の末に精神が壊れてしまったら?心配なんてものじゃない。
「じゃあ騎士団なんてやめてパーッとどっか行っちゃう?」
わたしはシリウスのその発言にむくりと起き上がって、目が点になってしまった。あなたの大好きなジェームズもすべて放り出して?またあのきらめく青春時代のようにどこかで日々を送れるの?わたしのあまりにもマヌケな顔にシリウスは思わず吹き出して笑い出した。
「なーんてな、放り出すなんて無理だけど。いつか世の中が平和になる時が来るから」
「来るから?いつ?いつ?」
「そりゃあお前ヴォルデモートがいなくなったら、だろ?」
学生の時のようにあどけなく笑うシリウス。そうやってわたしの不安を消してくれてきたんだよね。ぎゅうっとシリウスの足に子どもみたくしがみつく。シリウスは「邪魔だなー」と言いつつニヤニヤしているのをわたしは知ってる。こんな幸せなひととき。今世の中が平和じゃないなんて信じられない。外を歩けば、死喰い人の罠が待ってて。呪いが飛び交う暗い街。でもこの人を信じてわたしは平和を探すんだ。いつかあの時のようなきらきらした日々を取り戻すんだ。
「シリウスのばか」
「おい、何でバカだよ」
「だいすき」
「・・・ああ、知ってる」
この人と、探すって決めたんだ。わたしを取り巻くすべてが優しかったころはもう帰ってこないけど。あなたと一緒なら、すこしだけ世界が良いものに思えてくるね。お砂糖ひとさじ、甘いひととき。お塩ひとつみまみ、しょっぱい涙。胡椒ひとふり、スパイスがちょっと辛すぎるけど。素敵なものいっぱい鞄につめて、あなたと一緒にでかけよう。世界がもうすこし、優しくなったころに。