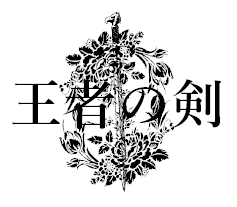
|
俺には己との戦いこそが至高のものだと信じていた時期があった。俺は個としてテニスに向き合い、剣の道、居合の道、それらの集大成をテニスで実現したいという志を抱いていた。何者にも惑わされず、お祖父様から譲り受けた道こそ己の誇りと信じ、突き進んでいた。あの時までは。俺は、齢十二の時幸村精市という神童のような選手に出会う。それが俺にとっての人生の大きな分岐点を指し示す存在になるであろうという事を知らずに、俺は幸村にテニスで屈する事となる。俺はあの時ほど自分の力の無さをまざまざと感じたことはない。己を磨き上げる鍛錬を更に課し、立海大附属中学校へと入学することとなった。 立海大附属に三年いる間、これほどまでに幸村の存在、手塚の存在、跡部の存在…好敵手たちの存在を意識せずにいられないということはなかった。俺は己と戦うと同時に他者との戦いさえも選んでいた。いや、むしろ他者との戦いに重きを置いていたのかもしれない。本当に危ぶむべき存在は自分だったのだと、幸村が病に倒れた時に思い知ることとなる。俺の刃は他者へと向けられるべきものではない。それこそ嫌な言い方だが、他者を利用し己に勝つことが俺にとっていかに最優先事項だったのかと今の俺は過去の自身を見つめ愚かだと感じている。 俺は手塚にはなんとも言えぬ感情を抱いてきた。それは畏怖なのか、それとも彼への対抗心なのか。尊敬できる存在であるのは確かだ。倒したい相手の一人であるのは間違いない。ずっとわだかまりを感じていた、奴を倒していないという事実に。だがしかし、…三年目の全国大会の時にその時はやってきた。我が王者立海大附属は関東大会では準優勝という屈辱を受け、全国大会へ挑戦者という立場で臨んだ。なんとも三連覇を成し得ないといかん。自分の中でもその事実が揺るぎのないものとなっていった。だが、しかし。手塚と俺が対面する時がやってきた。いざ、行かん。そう俺はコートへ足を踏み出した。真っ向勝負が、俺の十八番。皇帝の名に恥じぬ、戦い方である。 俺は甘かった。俺の読みは浅く、そして甘くもあった。手塚はチームを優勝に導かんという想いだけで腕を犠牲にしようとした。それだけの覚悟が手塚にはあった。俺自身にもあった。だがしかし、幸村の一言で俺の自身が揺らいだ。真っ向勝負を捨てる、その時が来るというのか。その残酷な事実に向き合い、己の鬱血した両脚を見る。手塚を見やる。奴の腕もまた、手塚ファントムのおかげで鬱血していた。ベンチに座りながら幸村の闘病生活が蘇る。我々は幸村との約束を、関東大会では果たせなかった。その報いだ、これは。 俺は卑怯だ、と聞こえる声さえにも耳を塞ぎ、自身に目を瞑り、俺は立海大附属を優勝という栄冠に導くために己の勝負を捨てた。立海大附属を勝利に導くために俺は自身の勝負を捨てた。酷使しすぎた脚はもつれながらも走り続ける。 俺は果たして三連覇のために生きてきたのか――― それとも己の勝負のためにテニス人生を送ってきたのか――― 葛藤しながらも球の回転を見届ける。皇帝の名などお飾りなだけだ。俺は屈する。手塚にではない、己にだ。そうだ、それが正しい。俺は立海大附属を勝利に導く、それが正しい選択なのだ。 奴ももう零式サーブは打てまい。そう思った瞬間だった。手塚の瞳から僅かな光が見えた。俺はそれを見逃さない。 「零式サーブだ!!」 幸村の声が聞こえる。奴は死んでいない。俺がじわじわと毒を回すような戦法をとったのにも関わらず。俺は己の敗北が頭によぎった。ネットの上を転がる球に会場全体が息を呑む。俺はあがき続けた。脚がどうしても動かない。己の信念はあの球へと進んでいるはずなのに、脚が動かん。これほどの悔しさ、屈辱感、緊張感、克己心への裏切りを味わったことはない。だが俺は死んでいない。俺だって生きている。俺は全身全霊で声を張り上げた。 「向こうに入らんかーーーーーーーーーーっっっっ!!!!!!!」 一瞬の静けさ。球が落ちる。落ちた場所は、俺のコートではなかった。 試合に勝って勝負に負けた、まさにその言葉通りだった。だが俺は心の底から自然と湧き出てくる喜びには抗わなかった。複雑な、何としても複雑な、そんな想いだった。勝負が終わった。試合も終わった。手塚がドイツへ行くと聞いた時に俺はあの日のことを思い出し、やっと手塚が自身のテニスのために解放されるのではないかと思えた。 俺は……あの日、便所で行き場のない感情のために涙を流した。嗚呼、そうだ、俺はまだ己に勝ててはいない。己の可能性や己の行く末さえも分からない。己との戦いを終えることはないだろう。俺は王者の剣をどこかで携えているはずだ。そしてそれを掲げる時、俺は自身の戦いの勝利に己を鼓舞し、そしてまた腰にその剣を携え突き進むのだ。それが俺の、信条、生き方、俺自身なのだ。 |