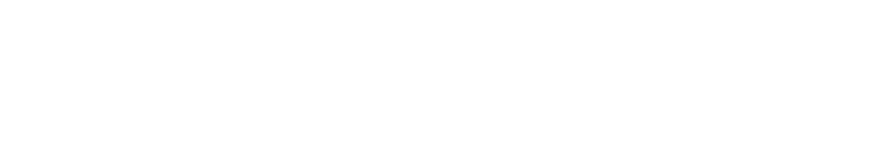皆が寝静まった頃の、談話室。パチパチと鳴る暖炉の火の明かりがぼうっと談話室を包んでいる。他学年の生徒は皆大人しくベッドへ向かったけれど、数人の生徒が談話室で羊皮紙とにらめっこをしたり、机に突っ伏している。図書室のゆったりとした空間でカリカリと鳴る羽根ペンが羊皮紙を走る音が好きで、いつもは自分のペースで図書室でレポートを終わらせる僕も、今回ばかりは難航していた。なにせ魔法薬学のアモルテンティアの成分とその作用のレポートが二巻き、無機物が呪文によって動力を有す理論を二巻き、という至極難解な教科の課題が出されてしまったのだ。僕はハニーデュークスで買った新製品の蜂蜜ヌガー入りのチョコレートをかじりながら残りの一巻きを終えようと机についた。机についたはいいけど、大事な事を忘れていた。いつだって紅茶を淹れないと僕の勉強時間は始まらない。重い腰を上げると、ニコニコとトレイにティーポットとティーカップを二つ乗せ、傍によく見知った女の子が立っていた。
「リーマスが紅茶を飲みたい頃だと思って」
「・・・・・・僕に変身術、教えてもらいたんだろう?」
「バレちゃった?」
あまりの手際の良さに僕は仕方ないなあと笑いながら散らかっていたところを片付け、の分のスペースを開ける。香りの良い紅茶に今日はベルガモットの紅茶を淹れてみたよと微笑む隣のの魂胆はわかってるとは言えど、好きな子に紅茶を淹れてもらえるだなんて幸せだ。僕は浮かした腰を再び椅子につけると、目の前に重なる本と羊皮紙の束に思わず小さなため息がこぼれた。
「い、嫌なフレーバーだった?」
「え?あ、いやそんな事はないよ。ただレポートが憂鬱でね…ってさっさと始めないとその憂鬱も終わらないか」
苦笑いを浮かべつつ、何故か目が少し泳いでいる彼女に僕はいささかの違和感を抱いたけれど、チョコを割って差し出した。
「これ、ハニーデュークスの新製品。食べる?」
「う、ううん、こんな夜に食べると太っちゃうし…ありがとうリーマス・・・ごめん」
尻すぼみに話しながら肩をすくめる彼女は何故か謝りだした。僕はレポートの内容がそんなにも分からないものだったのかな、と思いながら羊皮紙と参考文献を開く。彼女がトレイを抱えたまま僕を見つめるので色んな意味での居心地の悪さを感じムズムズしていた。
「レポート、やらないの?」
「や、やる。トレイ、片付けてくるね」
言葉にどもり、僕を見つめたり、慌てて立ち上がったりなど挙動不審な様子。何かがおかしい。いつもなら目をパチクリとさせ、きょときょとと忙しなく小柄で小さな手足を動かしている彼女だけど・・・・・・。と思ったけどそう考えるといつもと違うわけでもないか。僕は自分をそう納得させ、彼女が淹れてくれた紅茶を一口飲むと紅茶では感じられない苦味を舌に感じた。思わずむせそうになったけど一応喉を通り一気に飲み込んだ。彼女が淹れてくれた香りこそは柑橘の爽やかな匂いがするが紅茶とは言え・・・これは非常に不味い。というより、紅茶なのか。紅茶ではない。これは・・・もう一口飲むと、予感が的中した。
「・・・コーヒー」
「・・・えっ」
「これはブラックコーヒー・・・」
「うん・・・」
自分の瞳がギラギラと彼女を睨んでいる事に気がつく。ブラックコーヒーは僕は嫌いだ。苦いだけで…湧き立つ香りなんて僕は味わえない。たまに一緒にお茶する彼女もそれは十分承知のはずだ。
「ブラックコーヒーでブラックなイタズラ、なんちゃって」
「・・・・・・」
僕は思わずその言葉に吹き出してしまった。そんな寒いギャグを飛ばすだなんて思いもよらなかった。は先程コーヒーより苦い顔をしていた僕が急に笑い出したものだから、怯えた瞳が急に半三日月の形になりいつもの素敵な笑顔を見せてくれた。僕が大きな笑い声をあげているものだから、机に頭をもたげていた生徒達がむくりと起き上がって呆然と僕達を眺めていた。
「ご、ごめんね・・・?」
「ああ、もう、いいよ・・・・・・さ、レポートをやろう」
そう、こうやって突拍子もなく僕を笑わせてくれる君が好きだ。憂鬱なレポート、それに向かう気だるげな生徒たち。そんな雰囲気も、吹き飛ばしてくれる。君が、好きだ。僕は幸せな笑みをたたえると、顔も渋るような苦いコーヒーを飲みながらを席に呼び戻した。
後でそのジョークが、シリウスからの入れ知恵だと知る事になる。
・・・・・・まさにブラック・コーヒー。