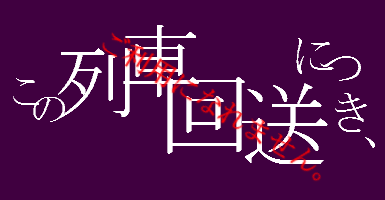た、と手を止める。ゆっくりと上司の顔を見上げて、再び先ほどの言葉を繰り返すように視線を向けると上司ははぁ、とやるせなさそうな溜息をついて再び先ほどの言葉をゆっくりとなぞらえる。わたしは己の耳を疑った。
た、と手を止める。ゆっくりと上司の顔を見上げて、再び先ほどの言葉を繰り返すように視線を向けると上司ははぁ、とやるせなさそうな溜息をついて再び先ほどの言葉をゆっくりとなぞらえる。わたしは己の耳を疑った。「シリウス・ブラックが亡くなったそうだ。名前を呼んではいけないあの人も帰って来たらしい。」
「・・・シリウス・ブラック、ですか?」
「あぁ、先日の死の間での戦いを知っているだろう、君。彼も不死鳥の騎士団に所在していたらしい、シリウス・ブラックは無実だったのだ。しかしそんなのはどうでもよろしい。それよりも名前を呼んではいけないあの人だよ、君。」
ファッジは本当にそれが何事でもないかのようにその後の問題を淡々と述べていく。わたしはファッジがその事を告げた時からもう頭の中では何も循環しなくなっていたのだ。音と成している上司の言葉も泡沫の彼方に消えていって視界には走馬灯のようにホグワーツでの在りし日がフラッシュバックされる。
「それでだね、君・・・私もこの失態を認めなければならない。大臣を辞任するので直ちに手配を整えてく・・・君?聞いているのか?」
「あ、はい、大臣。手続きですね。今すぐメディアの方にと本部の方に連絡をつけます。」
「それと君のポストは無事だろう、ルーファスも君には目をかけてきた。副大臣のポストは保障される、安心したまえ。」
ファッジはわたしが自分のポストについて心配でもしているのかとでも思ったのかそのような言葉をかけてくれたが、それは全くの的外れな慰め。ルーファス・スクリムジョールが次期大臣になる事はもう目に見えている事だった。今の大臣はただのみすぼらしい老人にしか見えない。深く刻まれた皺はわたしを思いやるように緩められ、ぽんと肩を叩かれる。去り際に「ご苦労様だった」と小さく呟いたのが肩越しに耳に入った。
けれど、そんな事も全て遠く彼方で自分が他人事のように見ているようにしか思えない。今わたしの頭の中全てはシリウス・ブラックだけで埋め尽くされていた。
シリウス・ブラックとは何の関わりもなくわたしはホグワーツでレイブンクローの主席として過ごしてきた。7年目に彼の友人、ジェームズ・ポッターにそれが奪われた時の悔しさは今でも覚えている。12ふくろうを取るのがわたしにとって生きがいだった。常に勉強という点で皆の尊敬の眼差しを浴びる事だけが誇りだった。けれどそれはあくまで見せかけの自分でいつも自由に過ごしている悪戯仕掛け人と呼ばれていた彼らがとてつもなく、眩しかったのが脳裏に焼きついて離れない。
自分でも言うのは何だけれどそこそこモテてはいたと思う。顔だって悪くはないし、才色兼備の名を時折耳に挟む。その称号を鼻にかけ、憧れの彼にも振り向いてもらえると過信し過ぎていた。彼の周りにはいつも可愛い子ばかり取り巻いていて、でも本命はいないと巷の噂で有名だったのもあり、知っている。でもその視線はいつもわたしに向けられていると思っていた、そんな愚かな自分の思想を信じて疑わない自分。何もせずに日々は過ぎて行く。そうして何もせず、何も得ず、無駄な期待を胸に抱きそれは脆く儚く散り行きわたしは絶望に打ちひしがれた。
ずっと彼だけを見つめていた、でも彼はそうではなかった。わたしが付き合っている人がいても、わたしの視線は常にシリウス・ブラックへと向けられていた。恐ろしいことにわたしは知らず知らずの内に彼に心を奪われていたのだ。体を重ねた相手は何人もいた。けれどその向うにはシリウス・ブラックだけがいる事を信じてわたしは行為に流されてゆく。
卒業後、彼の進路など知る由もなくわたしはエリートコースを歩み、入社してたった2年で魔法執行部の部長へと移り、ボーンズがわたしのポストを受け継いでからは4年後に副大臣へと就任し、今ここに至る。決してわたしが大臣になる事はないと分かってはいたがこの世間でも大臣の影に隠れしかし給料も大臣並に良く仕事もそれとなくこなせば良いという安全なポストにわたしは満足していた。空虚を振り払い、結婚もせず親の孝行に尽くし、そして独り老い行く。敷き詰められたレールを辿れば着く終着点。
彼に思いを馳せ早19年。片時も彼の事を想わない日はない。しかし今、わたしは岐路がレールのすぐ近くにあった事を知った。後ろをゆっくりと振り返り、ホグワーツという停車場を見渡す。横に小さな小道がある。それが何本にも枝分かれし、やがてそれは視界の彼方に消えここからでは見えない。あの時何か行動を起こせばわたしはあの岐路へとのレールへ方向を変えれたのか、否か。手を伸ばせばすぐそこにあったものも今のわたしには遠すぎる。目を凝らさなければ見えない程に。
彼はわたしの全てだった。彼が悪戯を成し終えて子供みたいに友人らと笑う姿も、女の子を連れクールな顔を装っていた所も、家を出たと噂が飛び交う中清々しくスリザリンを罵っていた時も、わたしは肩時も彼から目を離す事はなかった。周囲からはポーカーフェイスと言われていたわたしがそんな感情を抱いているとは知らずに彼らはわたしをもてはやし、わたしは同時に良い気分となる。数え切れないほどの男に抱かれ、幾千ものキスマークを体に刻み親言うとおりに勉強に時間を費やし優等生のお面を被った娼婦も同然。虚しい思いを抱え、彼に抱かれ、愛される事だけを夢見て来てようやくこれ。
彼がアズカバンに囚われた時さえわたしは彼を愛していた。ファッジと共に彼を窺う機会はあったけれどわたしが発した言葉はほんの二語。シリウス・ブラックはファッジが持っていた新聞に貪りつきそんな様子をわたしは周囲には呆れたように見えたかもしれないがわたしこそ彼の様子を目で貪っていた。
そんな彼が、死んだ。結局彼は裏切り者でも何でもないただの無実で無垢な者で、そして戦い往ってしまった。そしてわたしの上司はそれをどうでもよいと言う。否、最早元上司である。新しいスクリムジョールは果たしてそこまで権力に搾られないような人材なのだろうか。
今まで振り切ってきた心に空いた穴がいつのまにかわたしの足元にあったと気付くのはビルの屋上の上での事。
今まで過ごしたイギリスの街の臭い排気ガスが交じった胸糞悪い空気を深く吸い込む。がたんがたんと潤滑にレールを辿る列車の車輪は、音をも無くし、