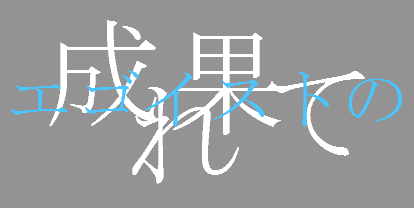と、気がつくと目の前には日刊預言者新聞などで見慣れたみすぼらしい老人が俺の目の前に立っていた。アズカバンはとんでもなくジメジメしていて、樹海の迷路のように道が曲がりくねっていて、人かも分からない狂気と何とも言いようがない人の醜悪さが満ち溢れた所だ。
と、気がつくと目の前には日刊預言者新聞などで見慣れたみすぼらしい老人が俺の目の前に立っていた。アズカバンはとんでもなくジメジメしていて、樹海の迷路のように道が曲がりくねっていて、人かも分からない狂気と何とも言いようがない人の醜悪さが満ち溢れた所だ。ファッジはどうやら俺の様子を見に来たらしい、何ともお世話様と言うところであろうか。俺には最早何の希望も何も残されていない。無実だと自分に言い聞かせる事で吸血鬼の拷問から自我を守り、そしてジェームズにそっくりなあの小さなハリーだけを気にかける。未だ彼らが亡くなったなど信じたくない。悪夢だ。それこそ狂気の沙汰だ。
ファッジが俺の前に姿を現すと、2人の連れがいて、格子から洩れる光を頼りに俺は彼らの顔を確認する。するとそれは予想もしなかった奴が今、俺のまん前に現れた。もう一人は監修であろう
「・・・ブラック、調子はどう?」
「・・・まぁまぁだ。」
「アズカバンでの生活も悪くないって事かね?いやそうでもなさそうだな。それでだ、ブラック・・・」
平静を一応装って俺は彼女の問いに受け答えたがすぐにファッジのそのしわがれた声によってすぐに会話は遮られ・とはそれ以上言葉を交える事は二度となかった。大臣の言う事は殆んど世間話に近い話で、けれども俺が未だ正気を保っている事にかなりの関心を示していたようだ。しかし、俺はそれよりも・がこのおいぼれの傍で佇んでいた事に驚いている。
・、彼女は
いつのまにか目の前には・だけが艶麗に微笑んでいて、ルージュに塗られた唇が俺に囁きかけることだけを望み女を抱いた。虚しさと切なさと恋しさを胸に抱きながら俺は何人もの女を抱く、毎晩抱く。毎日違う女だった時もあったしそれが1週間ごとであったり期間はまちまちだったがそんな事は今更どうでもいい。いつのまにかあの色という魔力の宿った黒の瞳に俺だけを映すように祈り、請いながらブロンド美人らをこの胸に抱きそして欲望だけを満たす。流れる汗を眺めながらこれが・のものならどれだけ美しいのだろうかと何度も思いに馳せた。
こんなにも奮い立たせる女は初めてだったが、・に俺は話しかけようとしなかった。たまに感じる視線もそれは俺の背後へと突き抜けていくものだと思い、あの美しく端整な唇に俺の名が知らず知らずに語られる事なんてないと思っていたからだ。彼女の周りには常に手ごろの良い俺と同レベルと言っても良いぐらいの男共々、そして彼女の美しさと聡明さに恍惚な視線を送る女共々。・はいつもレイブンクローの輪の中心へと佇みそして満足そうに日々を過ごしているかのようだった。
それをあの時になってようやく、彼女と初めて言葉を交わす。まるで・に話しかけられた時は幻想の世界へと飛ばされたかのように現実味がない。先ほど見せた小さな笑みも今はただの無と帰していてあえかなる彼女の顔は何も語らない。ひっそりと大臣の傍に佇みそして俺を見据える。アズカバンに納められるよりもはるかにそちらの方が苦痛だ。・に見つめられる事が苦痛なのではない、自分に対する悔恨と情けなさに苦痛を覚えるのだ。彼女の視線が矢を射るように突き刺さる。あぁ、彼女はまだ変らない。未だとても美しいまま。
しかし俺は何という様であろう、食事も食事と言えないほどのか細い「餌」であるし第一ここは監獄だ。風呂など何も体を洗う物もない。きっと俺の頬は痩せこけて無様な姿であろう。異臭が漂っているのも自分で分かる。その時、俺はあの諸悪の根源あの憎らしい小指がかけた鼠、ワームテイルことピーターがファッジの持つ新聞に飄々と何とも図々しくウィーズリーの連中と共に載っているのを見つけた。これには俺は憤激し、その新聞を渡すように頼み貪るように見入った。新聞をファッジに返すと横にいる・が呆れたような顔をして俺を見ていたが俺が彼女の方を見た瞬間すぐに彼女は顔を逸らした。彼女のように魔法省で成功している奴なんかに俺の気持ちが分かるわけがない。そのまま何もせず、何も得ず、そうして再会の場面は流れるように過ぎ去ってしまった。
今、彼女はどうしているだろうか。大臣に付き添うぐらいならばきっと副大臣か大臣補佐などのいい職についているだろう。12年も前の事だ、はっきりとは覚えていないが彼女が見に付けているものは高価そうなものばかりだったと思う。でも、あの細くて白い左の薬指には指輪も何も飾られていなかった事だけは鮮明に覚えている。あれから彼女はいい相手でも見つけたのであろうか。彼女は幸せでいるのか、そんな事を思い浮かべながらも俺はすっかり痩せ細った腕を目の前に掲げそして杖もなく、呪文もなく魔法を己にかけていく。やがて腕は全て毛に覆われ、骨ばった間接は隠せないにしても完璧となる黒い犬へと変貌する。
アキ・トキエダの髪と瞳と同じ色の、黒。するりと格子を抜ける体が虚しい。女を代わる代わる抱き、そうして彼女に毎晩思いに馳せていた時の力強さと虚無感が懐かしい。
そして、俺は今あの小さなハリーに会うべく、そして憎くてたまらないピーターを殺すためだけにホグワーツへと向かう。易々と暢気に過ごさせてやるものか。ジェームズとリリーを、そして俺の人生を。あいつは。けれど、けれど。もし、道中に・に会う事があれば、彼女に見つかるような事があれば彼女に捕まり、その白くて細く美しい手で殺されても、