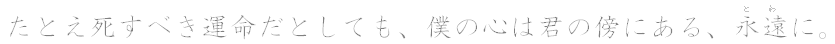競技場の外でレギュラスに絶対に勝ってねと、魔法で花冠を出して王様のようにかぶせてあげた。レギュラスったら、それを恥ずかしそうに外して「分かったよ」としぶしぶ頷いた。わたしはその姿に満足し、競技場の観客席に向かおうとした。レギュラスはチームで集合していて、わたしが誰かに話しかけられているのは都合よく見えなかったようだ。
「、ちょっといい?すぐ終わるから」
そう、いつものアレだ。こんな時にまで一体何なんだ。わたしは断るともっと面倒くさい事になることを知っていたので、彼女らに大人しくついていった。レギュラスの試合開始まで、あと十五分程度かかるだろうし。わたしは昔から何かと先輩たちに目をつけられていた。それも同じ寮の、スリザリン生から。我が強いスリザリン生はどうやら陳腐な連帯意識が強いらしく、それをくだらないと一蹴したわたしはあぶれ者だった。
「落ちぶれた家の小娘が、ブラック兄弟と楽しくお喋りしてんじゃないわよ」
「さっきだって馴れ馴れしくレギュラスをからかうようなことして、レギュラスだって迷惑そうだったじゃないのよ」
「ロジエールも貴方の家は甘い蜜にたかる蟻のようだって言ってたわよ」
禁じられた森の近く。森は気味悪くざわめくけれどこんな事にビビる可愛い女じゃない。大体ロジエールが何よ。あんな陰険な奴に何言われたって痛くも痒くもない。けれど、わたしの家がブラック家に頼り切っているのは事実。わたしがこの秘めた思いをレギュラスに伝えてしまったらレギュラスもきっと悪く言われるだろう。純血の旧家といえど、もう屋敷ですら抵当に入っている。おば様にもおじ様にももう迷惑はかけられない。けれど、今までの非難を受け止めてしまうのはわたしの意地が許さなかった。
「大体迷惑そうだって誰が決めたのよ。これだからパラノイアが激しい女は好きになれないわ」
「なっ・・・貴方の家がブラック家の名に泥を塗ってるのは事実じゃない!!」
「それ以上何か言えば酷い顔にしてやるわよ」
わたしは杖を向け次があれば本当に蜂刺しの呪いをかけてやろうと身構えた。言い返せないわたしが悔しい。ブラック家の負担になっているのは事実。けれど、わたしはわたしがレギュラスの傍に居る事をどうしても否定されたくなかった。レギュラスの隣という居場所は、何としても死守したかった。
「あなたたちに付き合ってる時間なんてないわ。もう試合が始まるもの。寮杯がかかってるんだからあなたたちも応援するべきでしょ・・・」
わたしが競技場へと足を向け、台詞を言い終えないうちに視界は暗転していた。

「エネルベルト!」
馴染みのある声がわたしを蘇らせる。目を開けると、そこには脂ぎった髪が垂れて顔を覆い隠しているセブルスがわたしを覗き込んでいた。
「何よ・・・セブルス・・・いたっ」
「助けてやったのに何て言い草だ。・・・失神呪文をかけられたようだな」
「え?嘘・・・」
「嘘ではない。これだから馬鹿は・・・。状況をよく見ろ、試合はすでに三時間前に終わった」
「えっ?!試合は?!」
確かに肌寒さを感じる。時間が大分経過している証拠だ。セブルスは相変わらずのつんけんっぷりでわたしが身体を起こすとさっさと踵を返し、城へ向かった。でも助けてくれるだなんて、本当は優しいのよね。わたしはくすくすと笑いながらセブルスの早足に着いていく。腐れ縁ながらもわたしとレギュラスを見守ってくれるセブルスはわたしの大事な友人の一人だった。
「貴様を探していたようだ」
寮へ戻るとレギュラスがユニフォーム姿のままソファーで眠り込んでいた。それも昔のような、あどけない顔で。わたしは素直に愛しさが込み上げてくる自分の感情が憎いとさえ思ってしまった。身分の差がわたしを素直さから遠ざけている。いつだってレギュラスの隣でいたいのに、いつかレギュラスが誰か他の人のものになってしまうんじゃないかって怯えてる。レギュラスと話していると、心がくすぐったくてポカポカした気持ちになれた。そつなく何でもこなすシリウスと比べられて、兄が家督を継ぐ気のないのに苦虫を噛み潰したように悔しがる彼の後ろ姿だって見ている。
わたしは今日言われた事が事実で、それに抗えない自分に涙が溢れてきた。とっぷりと暮れた談話室に人は誰もいなかった。何度だって指摘された事はあった。その度小さな傷がわたしの心につくのを感じていた。けれどホグワーツ卒業まで残り2年、もうすでに塵はつもっていた。レギュラスに毛布をかけ、その整った顔の静かな寝顔を見つめる。ほんのすこし、弱音を吐いてもいいかな。涙がとめどなく溢れるのに、わたしは少し生きた心地さえも感じていた。今まで泣かないように、レギュラスに心配をかけぬようにと努めていた。だから、少しだけ。
「好きだ・・・」
それはとても甘い声だった。わたしの聞いたことのない、愛しい人の声。夢見心地にわたしは耳にしたことを反芻した。温もりが、頬を伝った。わたしが目覚めると、そこにレギュラスの姿はなかった。毛布は代わりにわたしにかけてあり、辺りの静けさからもう夜中なのだと分かった。すると、談話室の扉が開く音がした。顔を向けるとそこにはレギュラスが未だユニフォーム姿でティーポットとティーカップをトレイの上に乗せ、手にしている姿があった。わたしは先程の余韻が自分の耳にあるのを感じ、自分の頬が真っ赤に染まるのを感じた。
「起きたのか。今紅茶を・・・っ、?!」
わたしの足は咄嗟に動いていた。扉を荒々しく開けわたしは深夜の廊下へと飛び出していた。頭は真っ白になり、心臓の鼓動だけがわたしを支配していた。その時、不意に呼び止められた。
「!!」
「シリ・・・ウス・・・?」
「やっぱりじゃねえか。何だよこんな夜中に歩きまわって・・・フィルチに捕まってたらどうすんだ」
ブラック家を飛び出したくせに未だにこの傲慢な兄はわたしを妹扱いする。けれど、幼い頃からシリウスに可愛がられてたわたしは彼を邪険には出来なかった。いくらレギュラスに責務を全て押し付けたとしても、それはわたしの中での複雑な感情だったのだ。
「・・・こんな夜更けに徘徊してるのはシリウスも同じじゃない」
「俺はいいんだよ。日課だから」
「・・・とんだ日課ね」
「お前本当に可愛くなくなったな・・・って、泣いてたのか?何だ、レギュラスと喧嘩でもしたか」
「うるさいわねっ!!」
するとデカイ声出すな、とシリウスに怒られてしまった。別に喧嘩したわけではないけれど、今レギュラスの名を聞くにはあまりにもわたしは敏感になりすぎていた。そして、シリウスはわたしが彼を長年想っている事を知っている。本当に厄介な相手だ。
「今夜は優勝杯を勝ち取ったパーティだったんじゃないのか」
「・・・あいにく主役が眠りこけてたおかげでパーティは明日に延期よ」
「何だ、相変わらず間抜けだなあアイツは」
シリウスは何やら呆れたように答えた。家のゴタゴタを全部レギュラスに投げつけたシリウスには言われる筋合いはない。けれどシリウスがレギュラスをブラック家と切り離せずも憎みきれていないことをわたしは知っていた。
「お前が早くレギュラスと結婚してくれればクソババアも大喜びだろうよ」
「はあ?わたしがレギュラスと結婚なんて出来るわけないのはシリウスだって知ってるでしょう?」
「お前が嫁入りすればもうお前はブラック家の人間だろ。ババアはお前を気に入ってるみたいだし、家名もあるっちゃあるからそんなに悩む必要ないんじゃねえの?」
「そんな簡単に言うけれどね・・・」
「レギュラスがお前がいいって言えばババアも反対はしねーだろうよ」
わたしはボンっと顔が真っ赤に染まるのを感じるとシリウスがケタケタと笑った。このろくでなしはこうやっていつも人をからかう。
「俺が寮まで送ってやるよ。は一応か弱い女の子、だもんな?」
悪戯っぽく笑うまだ少年のようなシリウスにわたしはため息を吐いた。兄がこんなだから、きっと弟がああなのだろう。シリウスを見ているとあまりのお気楽さに腹が立つ。レギュラスの置かれている立場を考えずにあのマグル贔屓のポッターなんかと組んで遊びまわっているから。けれど、それを憎めないのもまたわたしの甘さなのだ。
「着いたぜ。もうこんな時間に出歩くなよ」
「説得力が全くないわね・・・まあ、ありがとう」
「レギュラス、お前に何か言ったか?」
「え・・・・・・」
わたしは先程夢で見た甘い声を思い起こす。再び耳まで赤くなったわたしを見て、シリウスは不敵に笑った。
「優勝杯を獲得したらお前と婚約する、だとよ。俺にこの前律儀にも報告に来たぜ」
「え・・・・・」
「あー、あいつは本当に愚図だなあ。あっ、これ言わない方が良かったか?まあいいか。どうせお前ら両思いなんだからよ。早くくっつけよ。その方が俺も安心だからさ。じゃあな、」
わたしはその場で呆然と立ち尽くし、シリウスの背が廊下の角で消えるまでそれを見つめていた。しかしわたしはフィルチの飼い猫の声が聞こえたのに驚き、急いで談話室への扉を開き中に急いで入った。頭が回らないまま談話室のソファーへと向かうと、レギュラスがローブ姿で座っていた。紅茶を片手に優雅にのんびりと。
「、どこ行ってたんだ?こんな夜中に出歩いてフィルチに捕まって減点だなんて笑えないぞ。せっかく優勝杯を獲得したっていうのにそれを無下にするなよ」
「う、うんごめん・・・」
わたしは赤い顔を隠すようにうつむいて女子寮へとそそくさと去ろうとした。先ほどの、シリウスの言葉は本当なの?レギュラスがわたしの名を呼ぶ度に心臓が跳ね上がる。さっきのまどろみの淡い夢は本当のことだったの?聞きたいけど、聞けない。だって、わたしは・・・。
「?どうしたんだ?具合でも悪いのか?」
「え、いや・・・えっと、あの・・・」
「・・・・・・まさかさっきの聞いてた?」
わたしはドキリと脈が波打つのを感じた。レギュラスの瞳が、いつものようなシニカルな色合いを含んでいなかった。それは穏やかで温かくて、そしてわたしを射抜くような瞳だった。
「き、いてた・・・」
「・・・・・・そうか。」
「・・・・・・なあに」
「僕と・・・結婚してください」
レギュラスはわたしの手の甲を取ると小さく口付けた。わたしは限界まで赤くなってしまっていた。それは熟れすぎた果実のように。けれど、わたしの長年のわだかまりが、その口づけでスッと溶けていった気がした。もう、わたしも素直に生きていいのかしら。
「・・・はい」
先程とは違う、喜びの雫が頬を伝う。月明かりに照らされて、わたし達は結ばれた。お互いの影と影が重なって、誓いのキスを交わした。わたしとレギュラスの、互いの永遠に誓って。